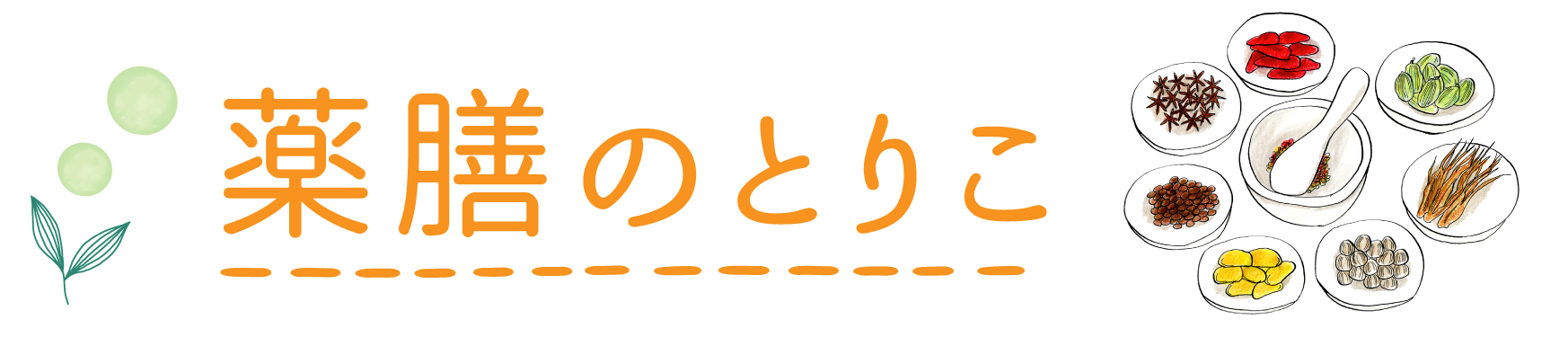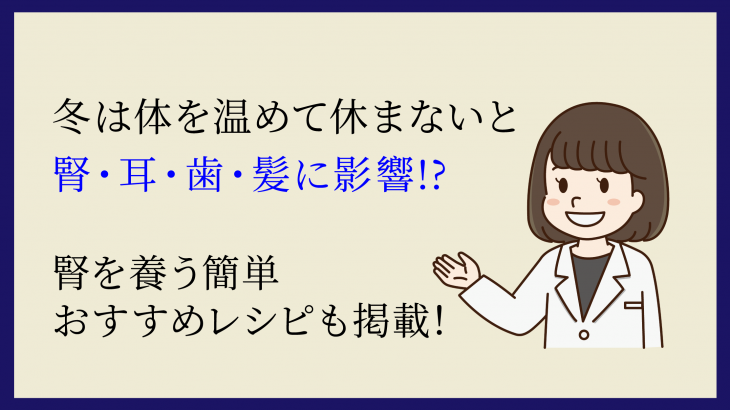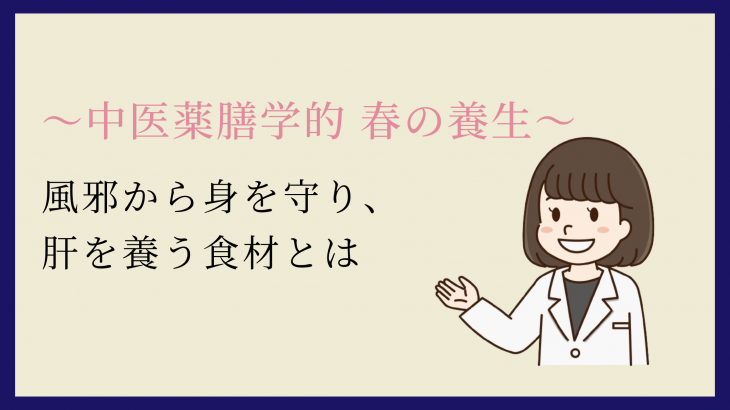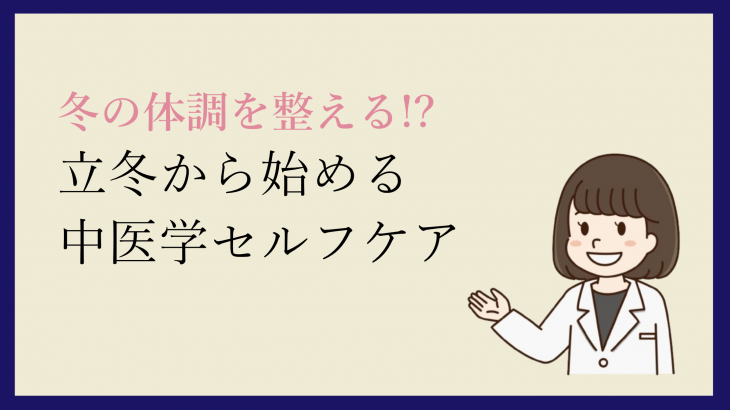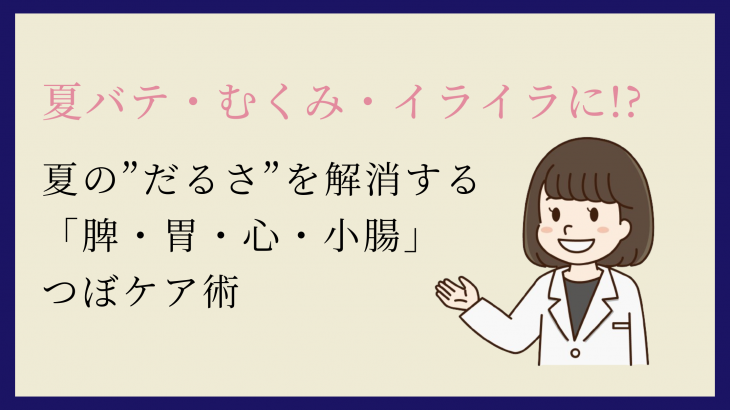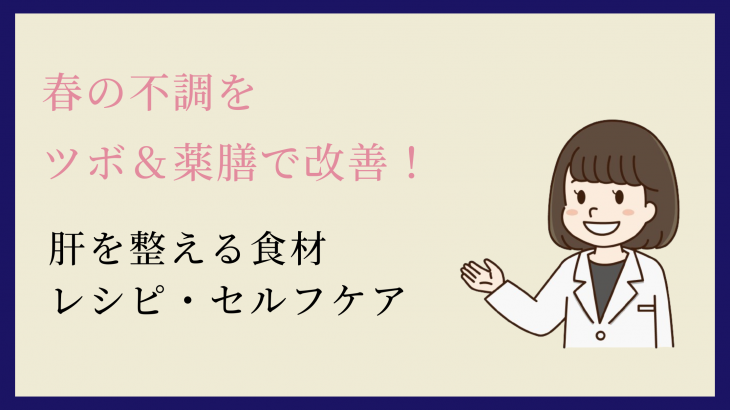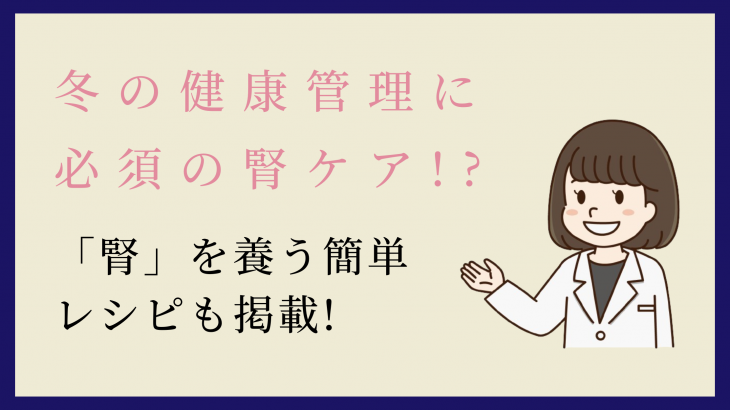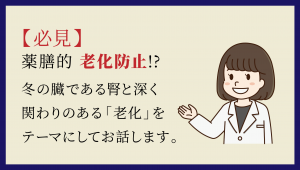冬の食養生
冬は立冬(11月初め) ~立春(2月初め)までの3か月間を指します。
自然界は陰気旺盛となり、一年で一番寒い季節であり、草木は枯れ動物は冬眠に入り体を休ませる季節です。
冬の邪気である寒邪は、五臓で言うところの腎を傷めやすいので、冬の養生は腎を養い、 体を温め、乾燥に注意し、 質の良い睡眠をしっかりとることが大切です。
腎とは、 生命の源である精 (親から受け継いだもの、 成長・発育・生殖等の生命活動)を蔵しているところです。また、腎は、吸い込んだ気を納め、臓腑を温める働きがあります。
腎が弱ると成長・発育・生殖等の生命活動に支障をきたします。
老化によって耳が遠くなる、 髪が抜ける、 白髪が増える、 認知機能の低下、歯・骨がもろ くなる、足腰が弱る等も、 生命活動を担う腎の衰えによるものです。
また、腎は水を司っており、 体内の水分代謝にも深く関わっているため、腎を傷めると、 むくみ、冷え、耳鳴り、難聴、めまい、下痢、便秘、頻尿、尿漏れ等のトラブルがあらわれます。
腎に対応する腑は膀胱であり、経絡において表裏関係にあります。
腎に属す色は、五色で言うところの黒です。
腎を傷めると顔色が黒ずんできたりします。
黒豆・黒ごま等の黒色の食材は、腎を養います。
腎に属す味は、五味で言うところの鹹味(かんみ・塩辛い味)です。
昆布・わかめ・ひじき・のり等の鹹味は腎を養います。
鹹味は腎の働きを助けますが、 摂りすぎは、五行において相剋関係にある心の働きを弱め、 心臓・血管のトラブル等、 循環器系に支障をきたしますので注意が必要です。
冬の養生 キーワードは、 『体を温め、ちゃんと休む』 です!
合わせて読みたい記事はこちら▼
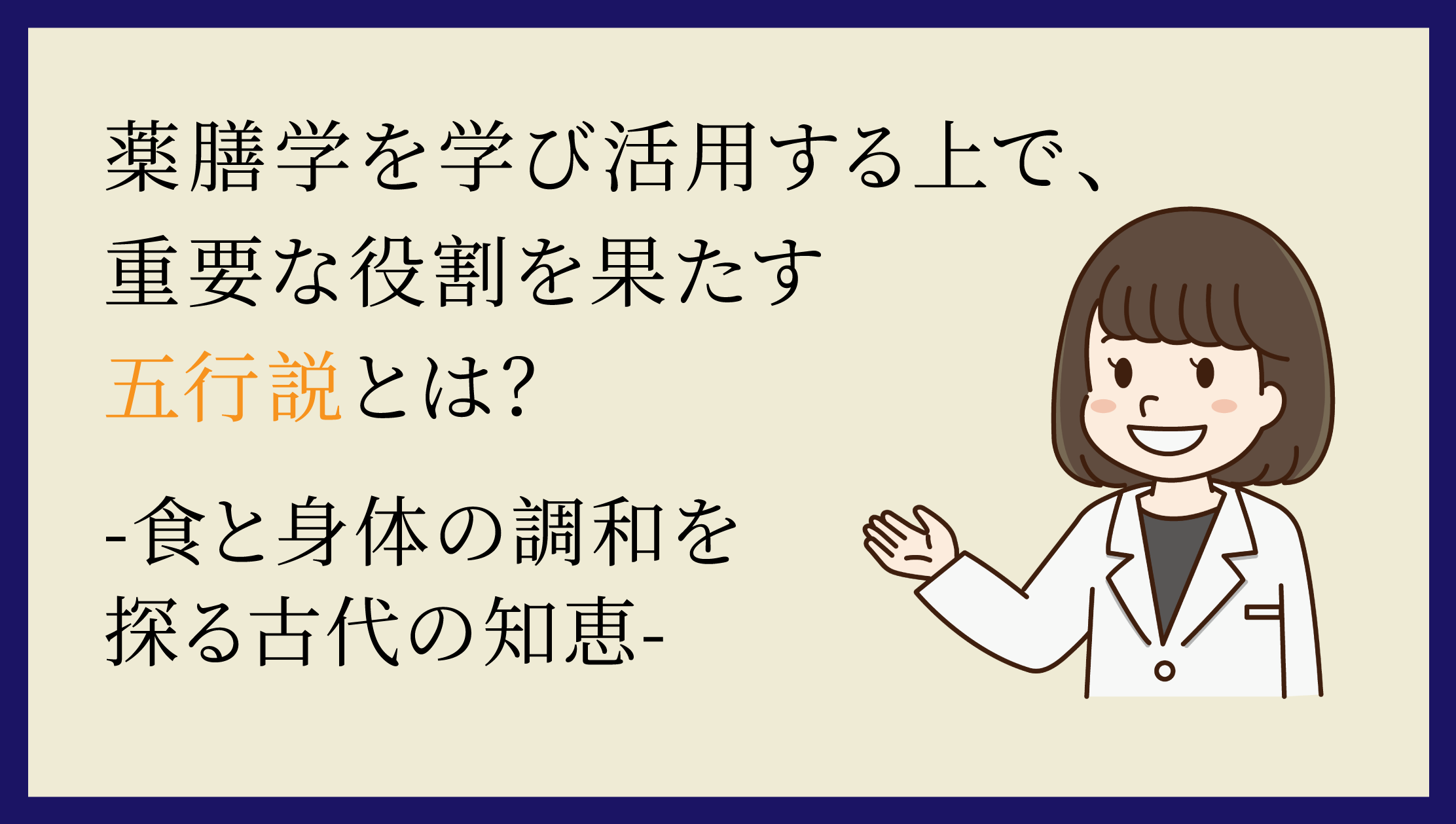
~ 冬のおすすめ食材 ~
☆気を補い臓腑を助ける
→ 米・長芋・じゃがいも・いんげん・栗・かぼちゃ・鶏肉・干しい たけ・キャベツ
☆体を温め陽気を補う
→くるみ・えび・ナマコ・ 羊肉
☆血を養い体を滋養
→にんじん・ほうれん草・ 落花生・ぶどう・ライチ・レバー・イカ・タコ
☆体を潤し渇きを癒す
→小松菜・白きくらげ・卵・松の実・ごま・ クコの実 豚肉
☆気を巡らせる
→たまねぎ・ らっきょう・ナタマメ・そば・みかん・きんかん・えんどう豆
☆血流を良くする
→チンゲン菜・酢・ウコン
☆体を温め冷えを改善
→にら 唐辛子・ピーマン・シナモン・あじ・サケ・乾姜・キンモクセイ・黒砂糖・コショウ
☆腎の気を養う
→黒豆・黒ごま・くるみ・昆布・ひじき・のり
冬の食養生✨腎を養うレシピ✨
☆~ローズマリー香る~ サケのホイル焼き☆

【材料】1人分
・サケ切り身 約100g
・たまねぎ 50g
・いんげん 2本
・カボス 小1個
・オリーブオイル 大さじ1
・塩コショウ 適量
・ローズマリー 適量
【作り方】
① サケの裏表に塩コショウを適量ふり、なじませる。
② アルミホイルを、材料すべてを包めるくらいの大きさにカットし、オリーブオイルを少量 塗った上にサケを置く。
③ サケの真ん中にカボスの輪切り1枚をのせ、上からカットしたたまねぎ、 いんげんをのせ、カボス果汁を絞り入れ、 オリーブオイルを回しかける。
④ ローズマリーをのせたらアルミホイルで包み込む。
⑤ オーブントースターの天板にのせ、250°Cで約15分焼く。(ご家庭の調理器具に合わせて やりやすい方法で調理してください)
サケ・コショウはカラダを温め、いんげんは気を補い、 たまねぎ・カボスは気を巡らせるはたらきがありますよ♪
☆腎を養う 黒のスープ☆

【材料】4人分
・むきエビ 約100g
・黒ごまペースト 大さじ1.5
・ほうれん草 1束
・しいたけ 中2子
・乾燥きざみ昆布 約20g
・生姜 ひとかけら約15g
・かつお節 5g
・オイスターソース 大さじ1
・クコの実 適量
・水 800ml
【作り方】
① ほうれん草は茹でて水にさらし絞って適当な大きさに刻んでおき、 生姜はスライス、しいたけは細切りにしておく。
② 鍋に分量の水を入れ沸かし、むきエビと生姜・しいたけを入れる。
③ 火が通ったら、ほうれん草、昆布、かつお節、オイスターソースを入れひと煮立ちさせる。
④ 黒ごまペーストを入れよく混ぜる。
⑤ クコの実を入れて出来上がり。
エビ・生姜はカラダを温め、ほうれん草は血を養い、クコの実はカラダを潤し渇きを癒し、黒ごま・昆布は腎気を養います。
ほうれん草はシュウ酸を多く含むため、 茹でてから使いましょう!!摂りすぎると結石の原因となりますので何に使うときでも 下茹でをしてから使うように気をつけてくださいね💦